ヘルタースケルター【岡崎京子】
ヘルタースケルター
こわれていく予感とスピード感
| 書籍名 | ヘルタースケルター |
|---|---|
| 著者名 | 岡崎京子 |
| 出版社 | 祥伝社(320p) |
| 発刊日 | 2003.4.20 |
| 希望小売価格 | 1200円 |
| 書評日等 | - |
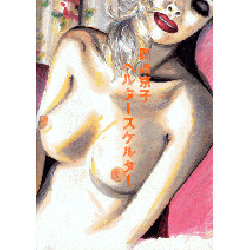
マンガ家の岡崎京子が酔っぱらい運転の車にはねられて執筆不可能となり、僕たちの前に新作が現れなくなってもう7年がたつ。(編集部注:1996年5月、事故遭遇)その間、雑誌「switch」が特集を組んだり、岡崎京子論やムックの岡崎本が出版されたり、未完の「untitled」が刊行されたり、その評価は高まるばかりだ。
そしていちばん待たれていたのが「ヘルタースケルター」の刊行だった。ボリス・ヴィアンの小説をマンガ化した「うたかたの日々」(宝島社)もほぼ同時に出版されたが、ビートルズには珍しく激しいリズムをもった曲の名前をタイトルとした本書は、とりわけ雑誌掲載時から傑作と評判が高かったものだ。
雑誌では読んでいなかった僕にとっては幻の作品だったので、発売されたと聞いてすぐ書店へ飛んでいった。最初に行った都心の大型店でも、次の書店でも売り切れで、3軒目でやっと手に入れて読み、そして圧倒された。
「pink」で人気を得、「リバーズ・エッジ」で若い小説家やミュージシャンにまで影響を与える存在となり、この「ヘルタースケルター」へと至る80年代末から90年代前半の岡崎京子は、あるゆるジャンルを横断してもっとも輝いていた表現者のひとりだったと断言できる。その同時代の息づかいは、7年たった今もまったく損なわれていない。
「ヘルタースケルター」の全編をおおっているのは、こわれてゆく予感と、それゆえに疾走するスピード感とである。主人公の「りりこ」は人気絶頂のスーパーモデルとして設定されている。彼女は「もとのまんまのもんは骨と目ん玉と爪と髪と耳とアソコぐらい」の整形美女。深夜、りりこが部屋の鏡で手術の後遺症のアザに気づき、「いやあああああ~」と悲鳴を上げるところから、物語は動きはじめる。
そのアザが顔から首筋、さらには全身へと広がるごとに、りりこは崩壊へ向けて行動を加速させてゆくのだが、これ以上、筋を追っても仕方がない。感じたことをいくつか、メモしてみたい。
まず気づいたのは主人公のりりこが、ほとんど線のみで描かれていることだ。僕はマンガのマニアックな読者ではないけれど、普通、マンガで人物を描くときは、髪や眉、瞳や唇、服の一部や靴などを黒あるいはグレーに塗りつぶして立体感を出し、コントラストをつけるものだろう。
ところがりりこはほとんどの画面で、髪も瞳も唇も、開いた口のなかすらも、また服も靴もすべてが線だけで描かれている。つまり、真っ白なのだ。平面的で、表面だけ「つるつるぴかぴか」で、なかには何も詰まっていない存在。主人公を線だけで描く表現は岡崎京子の他の作品にもあるけれども、りりこは際立っている。
そのかわりに、対照的に真っ黒につぶした画面のなかに、まるで無声映画のセリフのように、りりこの声にならない内側の声が流れる。「仕事なんてやめちゃえきみはぼくだけのものだ」と吹き出しで示される婚約者の御曹司のセリフにかぶせるように、「バーカ!!アホなことぬかしてんじゃねーよこちとらからだひとつでやってんだよ!!」といった具合。声にならない声はさらに反転して、「でもあたしはあんたを逃がさないわ」とつづく。
この黒い画面の独白は岡崎マンガではおなじみのものだけれど、ここではりりこの声だけでなく、他の人物の内面の声、さらには作者自身の声や書物からの引用が幾重にも重なって、層をなした声のポリフォニーで物語が進行してゆく。これは映画でいえばゴダールの手法だが、ともすればカタストロフへ向けて一直線に進みがちな物語を複雑で屈折の多いものにしていると思う。
映画的ということでいえば、インサート・ショットも素晴らしい。日本のマンガは手塚治虫以来、映画的手法を駆使して高度な表現を切りひらいてきたが、ここではビルの建築現場やマンションの夜景といった都市風景がひんぱんにインサートされる。
なかでも、仕事が減ったりりこの孤独な姿に、運河と高速道路のささくれだった夜景がインサートされ、ページを開くと見開きで、何の説明もなくキッチンで血だらけの女が殺されている、という展開には息をのんだ。
この作品で従来の岡崎京子になかった要素といえば、実際に起こった事件を思わせる病院の不正医療と、それを追及する検事を登場させたことだろう。
これは一方では、「女の子モノ」に奥行きと構造を与えるという働きをするけれど、他方、岡崎京子にふさわしからざる社会派的な視線を作品に導入してしまう危険をも持つ。またこの検事は、りりこに対する批評的な役割を負わされているけれども、やりすぎれば説明過剰というリスクもあるだろう。
そのあたりの危険を岡崎京子は、検事を単なる正義漢としてではなく、りりこの孤独や不安に感応する存在として、検事の夢のなかでは前世の兄妹として設定することによって、岡崎ワールドの純度を保っている。
そして見事なのはラストだ。りりこは崩壊して死ぬに違いない、という読者の予想を裏切って、岡崎はりりこを生き延びさせる(その生き延びさせかたもすごい)。
どんな希望のない世界でも、日常という戦場のなかを生き延びること。それは「リバーズ・エッジ」にも込められたメッセージだが、全編をおおう崩壊感覚と疾走の果てに転生して生き延びることを選んだ、りりこの最後のカット--黒い眼帯をかけ、チャイナドレスにニシキヘビをからませた--は美しい。
この最後のカットには、「タイガー・リリィ(りりこ)の奇妙な冒険の旅が始まっていたしかしそれはまた別の機会に」とあり、「to be continued」となっている。事故後、リハビリをつづけた岡崎京子は少しずつ回復し、この作品の刊行に当たっても目を通したという。いつか、りりこの冒険譚の続きが出現することを祈り、楽しみにしたい。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





