ヒト、犬に会う【島 泰三】
ヒト、犬に会う
| 書籍名 | ヒト、犬に会う |
|---|---|
| 著者名 | 島 泰三 |
| 出版社 | 講談社(266p) |
| 発刊日 | 2019.07.12 |
| 希望小売価格 | 1,925円 |
| 書評日 | 2019.11.16 |
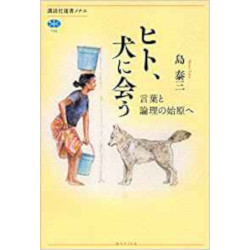
人と犬との関係は長い歴史がある、それは単なるペットではなく警察犬や牧羊犬を始めとした使役犬としての活躍の場は犬種を問わず多様である。まさに人間の良きパートナーという言い方が適切だと思うのだが、著者が熱く語っているのは「犬がいたからこそ、大型類人猿の一種『ヒト』は『人間』らしくなり…現在の『文明』にまで至った」という犬と人間の対等な関係である。著者は動物学者で日本ザルやマダガスカルに生息するアイアイという小型猿研究の専門家だが、本書では犬と人間の関係を幅広い領域からの分析と賛否を含めて多くの学説を引きながら精緻な説明を展開している。論文を読むような感覚で読み進んだのだが、一方、そこまで言わなくてもという「反論の表現」が有ったりするのも著者の「犬愛」の為せる業なのだろうと思う。
犬にまつわる興味深い事象がいろいろ紹介されているのだが、その一つが「歩く食糧貯蔵庫」仮説。その仮説とは1万5千年前に「イヌ」と「ヒト」は出会い、イヌの家畜化が進み、猟の協力者として、同伴者として、寝床を温めるものとして、そして時には食糧としてイヌが狩猟採集民に扱われていたと言うもの。「食糧」という言葉に一瞬違和感を覚えるが、犬食文化がある中国や韓国そしてオセアニアなどの地域の広がりを考えると、この仮説の存在を否定することも出来ない。
また、大分県での高度に訓練された紀州犬がイノシシと戦って倒すという特殊なイノシシ狩り、モスクワの地下鉄に乗って駅間を移動する犬、江戸時代のお伊勢参りの犬など、本当かと思いつつも人と犬のつき合い方の多様性を良く示しているエピソードである。また、犬は言葉を理解出来ず、名前を呼ばれてしっぽを振るのも単に音に反応しているだけという説に反論するかの様な事例が示されている。それは、初対面の犬に会うとき、事前に犬の名前を教えてもらい、初めて会った時に名前を呼ぶと犬は「なぜ、お前はおれの名前を知ってるんだ?」という驚きと怪訝な表情をするという。犬は単に名前を呼ばれて喜んでいるだけではないのだ。本当に怪訝そうな顔をした黒い犬の写真が添えられている。納得である。
本書が扱っているテーマは、「犬への変化」と題してイヌの起源を探りつつ、多くの学説を引きながら進化によるイヌの特性の変化を紹介し、「イヌ、ヒトに会う」と題してイヌとヒトが同盟関係を結んでいく過程を示し、「犬の力」と題して犬の特性を分析して人との共生の意味を解説。「ことばはどのように生まれたのか」という章では人と犬のコミュニケーションと言葉について語られている。
第一章は「犬への変化」と題してその起源が詳細に説明されている。食肉目としてネコ亜目とイヌ亜目の二つに分離したのが5600万年前。そして北米からユーラシア大陸に進出して100万年前にオオカミとイヌの共通祖が確立した後、「オオカミは人を襲わないという人間への許容度が高い。一方、イヌは人に対する高い親和性とともに、特定のヒトに強く結びつく傾向がある」という特性差を持ちながら独立していったことが判る。
第二章は進化してきたイヌがいよいよヒトと会うことになる局面で1万5千年前にオオカミ亜種のイヌがヒトにより家畜化されていく過程が示されている。
イヌが南下していって小型化が進んだ結果、イヌの平均体重はオオカミに比較しても半分近く軽くなっており、ヒトにとっては適切な大きさになっていた。また、イヌが多産であることや性成熟期間の短さといった生殖戦略はヒトが犬と共生するにあたって、仲間として適切な種を作り出していくための淘汰のサイクルが短いということも有利な点であったとしている。一方、ヒトは先行するホモ・エレクトウスやネアンデルタールの辺縁をさまよう直立二足歩行類人猿だった。
こうした特徴を持つ二つの種が同盟を成立させた理由は、ヒトとイヌ共に祖先種と比較すると小型で強力さに欠けているという相対的に弱いもの同士が結びついたものとされている。こうした環境でヒトは東南アジアに至って、ついに豊富な食生活を体験することになる。そこでイヌに与える食物もあり、イヌと共生することで他集団や大型捕食動物から逃れることが出来るといった相互関係により同盟が確立したと説明している。
第三章は「犬の力」と題して人と違う能力や特性を紹介している。犬は人と違って嗅覚、聴覚、味覚といったものだけでなく「恐怖」「凶暴さ」を匂いで嗅ぎ分けると言う。まさに人と別世界に居るということだが、味覚においても犬は水に関しては独特の味蕾があり水の味を感じることが出来ると聞くと、水をうまそうに飲む犬の姿にも納得がいく。また、犬の特性として集団行動の適応能力の高さこそ重要な点である。
こうした、人にない感覚能力、集団活動能力などを活用して、イヌから犬になった「犬」は人間社会でのみ生き延びられる存在となり、人間の意思を正確に実施しようとする特性を手にしたと言う。一方、ヒトは発達した大脳皮質前頭葉を使って全体的な判断を進化させてきたが、運動能力や感覚について高い能力を持っている訳ではない。このイヌとヒトの判断能力の違いを著者は、「犬は『人の仕草や物言い、匂い』など全体で客観的に判断するが、人は『第一印象』といった『幻想』で判断する」と説明している。
第四章は「ことばはどのように生まれてきたのかについて述べられている。犬は声道の構造から人間の様に子音+母音といった発声は出来ないが、犬は人の話言葉を理解する。言葉と言っても、「身振り」「音声」「文字」の三つの形態があるが、その中でヒトの最大の特徴を「ひっきりなしのおしゃべりだった」としている。こうしたコミュニケーション力の進化のステップの第一段階とは、まず呼びかけ能力として相手が応えるまで「作為的な呼びかけ」を続けることであり、次にヒトの言葉は「命令」の段階に入る。この時代は道具の利用の拡大など遺跡も多く残る時代だ。そして2万5千年前から1万5千年前頃にヒトは名詞と修飾語、命令語をつなぐことを始めたという仮説だが、それは考古学的に動物を表す絵が数多く描きはじめられた時代と一致するという。
その中で、犬とのコミユニケーションと言えば「身振り」と「音声」ということになる。主たるものは飼い主がひっきりなしに語り掛ける明瞭な「音声」によって主人の感情や意図を間違いなく察知する能力であり、いずれにしてもそれに従うかどうかは犬と飼い主との相性であったり、犬からみて尊敬や信頼できる相手であるかどうかという。この指摘は全ての人間関係においても成り立つ指摘であることが、また怖い所だと気づかされる。
そして、最後に人にとっての犬の存在について著者は次の様にまとめている
「犬は大好きな人の傍らに常にいるが、まったく異なった世界を見ている。それだけに、人は心が開放される。人が犬のそばでは信じられないほど饒舌になるのはそのためなのである」
本書の読書は、犬との生活の記憶とも重なり合って納得や驚きが続いた。中学生の頃、家で飼っていた秋田犬とコリーのミックス犬は長生きしたこともあり、懐かしさがいくらでも湧いてくる。もっと話しかけてやれば良かったと思うばかりだ。
犬に対する雑学的知識を満喫した読書であったが、気になる点が一つあった。それは、まだオオカミの亜種で会ったころは「イヌ」、家畜化されたイヌを「犬」と表記するとしており、同様に「ヒト」はホモサピエンスという人類種を示し、「人」は犬の家畜化以降のヒトを示すとしている。この説明を読んでいた時、「ヒト、犬に会う」という本書のタイトルは辻褄が合わないのではないかと思った。家畜化を起点とした表現の変化であれば「ヒト、イヌに会う」でないといけないのではないか。しかし、読み進むと第二章のタイトルは「イヌ、ヒトに会う」と整合性のある表記になっている。本のタイトルの表記は何か意図が有るのだろうか。また、考えてしまう夜の読書である。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





