ピアノトリオ【マイク・モラスキー】
ピアノトリオ
| 書籍名 | ピアノトリオ |
|---|---|
| 著者名 | マイク・モラスキー |
| 出版社 | 岩波新書(210p) |
| 発刊日 | 2024.03.19 |
| 希望小売価格 | 1,034円 |
| 書評日 | 2024.05.17 |
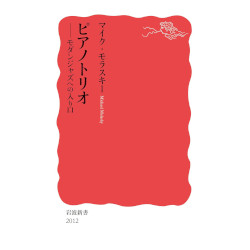
最初にピアノトリオを聞いたのは高校2年、同級生Uの家だったな。早熟なUはジャズのLPレコードを何枚も持っていた。かけてくれたのがオスカー・ピーターソン・トリオ『ナイト・トレイン』。1曲目がデューク・エリントンの「C・ジャム・ブルース」だった。太いベース音に始まり、ソとドが繰り返されるだけの単純なテーマなのに、ピーターソンが弾くピアノは当時の流行り言葉で言えば「こんなカッコイイ音楽があるのか」。モダンなブルースだった。それがジャズを好きになったきっかけ。
以来、半世紀以上ジャズを聞いている。だからジャズに関する本もずいぶん読んできた。「モダンジャズにおけるピアノトリオの発展史を概観」すると謳う本書『ピアノトリオ』のような入門書やジャズの歴史にも目を通した。でも書店でこの本をぱらぱら見て買おうと思ったのは、これまでと違う手法で書かれているから。例えば、こんな一節がある。ハンプトン・ホーズ弾く「アイ・ガット・リズム」の解説。
「この演奏こそビバップとブルースの両面が遺憾なく表現されているからである。まず、ビバッパー好みの三連符のフレーズや、二倍のスピードで弾かれるダブルタイムの長いフレーズも現れる(1:43-1:51;2:41-2:45;3:23-3:36)。しかし、ブルージーなサウンドを醸し出す方法もよく使われている。たとえば、ブルース音階中心のフレーズ(1:38-1:42;3:20-3:22)や、スラー(0:07;0:14;0:18)やトレモロ(0:19;0:39)や『溜め』(1:04-1:09)などである」
カッコ内の数字は、例えば通常の速さの倍の「ダブルタイム」で弾かれるフレーズが演奏開始後1分43秒から1分51秒の間に現れるということ。だからこの本、実際に演奏を聞きながら読むことを前提にしている。というより実際に聞きながら読むことで、これまで多かったジャズの印象論や抽象論でなく、具体的な音を聞きながらピアニストや曲を理解することができる。僕はこの本で取り上げられるアルバムを多少は持っているが、持っていないものはYouTubeで見ることができた。確かめたわけじゃないけど、すべての曲がYouTubeに(演奏タイムつきで)アップされている、いや、アップされている曲のみ選んでこの本は書かれたんじゃないだろうか。誰もがスマホでネットに接続できる時代だからこその書物と言えそうだ。だから一章読んでは音を聞き、次の章を読んでまた音を聞くというやり方で、新書一冊読むのに3週間かかった。今までにない読書経験でもあった。
取り上げられているのは1940年代のナット・キング・コール(彼はジャズ史に欠かせないピアニスト)やバド・パウエルから、いま「ジャズの神童」と呼ばれているジョーイ・アレキサンダーまで30人ほどのピアニストと曲。もっとも本書はあくまでトリオ編成にこだわり、僕がいちばん好きなセロニアス・モンクや、エレクトリック時代に欠かせないハービー・ハンコックは、「トリオよりカルテット以上の編成」を好んだという理由で取り上げられない。
マイク・モラスキーは、アメリカで生まれ日本の大学で教えている日本文学・文化史・ジャズ史の研究者、著書も多い(本サイトでも『ジャズ喫茶論』を相棒のUが取り上げている)。プロのピアニストとしてクラブに出演した経験もある。そんな著者が「録音の中の聴き処を数カ所に絞り、より具体的に記述」したというその例を、二人のピアニストに見てみる。
ひとりは、スイングするピアニストの代表としてウィントン・ケリー。もうひとりは、ケリーと対照的にスイングせずに美しい音を紡ぎ出すビル・エヴァンス。
ウィントン・ケリーの曲は「テンペランス」。「ケリー特有のスイング感は何より八分音符の弾き方に現れる」とマイクは言う。ちょっと細かくなるが、引用してみよう。
「同じ1-2,1-2,1-2,1-2と八分音符を弾く際、『1』の拍をどの程度伸ばして弾くか、どの程度アクセントをつけるか、スタッカートに近いタッチで弾くかレガートで弾くかなどという微妙極まりないニュアンスの違いが、各ピアニストのリズム感を際立させる。……ケリーは同時代のピアニストの中でも大きく『跳ねて』弾くため、ほかのピアニストとのリズム感の違いが際立つ。彼の八分音符の弾き方を人間の歩き方に喩えたら、ひどくぎくしゃくと歩いているようなサウンドと言える。ただし、ケリーの『ぎくしゃく』は限りなくスイングしているのだ」
そんな八分音符の弾き方として、1:13-1:20と具体例が示され、その部分を聞くことで読み手は、なるほど、ぎくしゃくとはこういうことか、と分かる仕組みになっている。「跳ねて」とは、1小節8つの音符のうち「1」を強く長く、「2」を弱く短く弾くということだろう。その強・長、弱・短のリズムがケリーだけのものであることによって、あの軽快な「ケリー節」が生まれる。
ビル・エヴァンスはケリーと反対で、「従来のスインギーなフォービート系のノリをあえて避ける」ことに特徴がある。小生の理解では、例えば八分音符の「1」「2」がケリーよりずっと均等に弾かれ、そのことによってピアノのリズムよりメロディが前面に出て、あの陶酔的なアドリブが生まれるということだろうか。著者はそれを「美しく繊細なタッチ、豊潤なコードヴォイシング、即興演奏におけるリリシズム」とまとめている。
さらに重要なのは、これはよく言われることだがエヴァンス・トリオがピアノ、ベース、ドラムの役割分担を変えたこと。従来のフォービート系のジャズは、ごく単純に言えばベースが4拍子のベースラインを、ドラムがリズムを主に担当し、ピアノがその上に乗ってハーモニーとメロディを担当している。耳になじんだ、いわゆる「ジャズらしいジャズ」。でもエヴァンス・トリオは、ピアノとベースとドラムが相手の音に呼応して対話する「インタープレイ」をつくりあげた。それを著者は名演と名高い「マイ・ロマンス」を例に分析している。
0:58-1:41のドラムとベースのバッキングで、ドラムはリズムを明白には刻まず、ベースはエヴァンスの弾くメロディに反応して「カウンターメロディ」を弾いている。ピアノのエヴァンスがまた、そのベースに反応してフレーズを弾く。「このようなベースの弾き方は、当時のジャズ界ではあまりに新鮮」で、「リズムセクション内の対話をもたらした」。またツービートやフォービートだけでなく「ブロークンタイム」(不規則のリズム)を用いて、「リズムに対してより柔軟な感覚を持ち込んだ」。
「マイ・ロマンス」は半世紀以上前、1961年に録音されている。この曲が収録されたアルバム『ワルツ・フォー・デビー』と、同日に録音されたもう一枚『サンデー・アト・ヴィレッジ・ヴァンガード』(僕はこちらのほうが好き)は、にもかかわらず、いま聞いてもまったく時代を感じさせない今日性をもっている。それは、エヴァンスが彼以後のピアニストに与えた影響がアフリカ系、非アフリカ系を問わず、いかに大きかったかということだろう。
この本は30人ほどのピアニストと曲を分析するだけでなく、冒頭に「ピアノトリオの聴き方」という章が置かれている。マイクは「音楽の聴き方は自由であり、様々である」と前置きした上で、ピアノという楽器の特質に合わせた聴き方のコツがあると言う。そのひとつは「パーツ別に聴く」こと。トリオでは、まずベースの音に注目するのがよい。なぜなら、低音のベースは目立たず聴きのがしやすいが、しかし「ベースがリズムとハーモニーの基盤を築くから」。同様にドラム、次いでピアノの音に耳を傾ける。ピアノでは右手と左手を個別に聴くとよい。ジャズピアノの基本は左手がコード(和音)を、右手がメロディを弾くことだが、それにとどまらず右手と左手を様々に使ったいろんな奏法が生まれた。右手と左手を個別に聴く訓練は、だからピアニストの個性を聴きわけることにもなる。
そんなふうにパーツ別に聴くとともに大切なのは、もちろん「身体でリズムを感じ取る」こと。ジャズのリズムやタッチやグルーヴ感(踊り出したくなる感じ)を受け取るには「身体の参加が不可欠」で、足踏みしたり指を鳴らしたりテーブルを軽くたたいたり、「どんな方法であれ身体を使ってリズムを感じ取ることが重要である」。
僕も3週間かかって何枚ものCDを聞きこんだ成果として、ピアニストの右手の音と左手の音がおおよそ分かるようになってきた。ドラムやベースが刻むリズムを足で取りながら、ピアニストが左手で別のリズムを刻むのをテーブルを手で叩きながら取るやり方も覚えた。50年以上ジャズを聞いてきた人間にも新しい刺激を与えて、もう一度ジャズをちゃんと聞いてみようと思わせてくれる本だった。
おまけもついてきた。ひとつは、YouTubeで本書に登場する曲を聞いていると、別のジャズ関連の動画を勧められる。それがまた面白い。なかで1995年にNHKBSで放送された「タモリのジャズ・スタジオ」は、モンクやウェス・モンゴメリーのお宝映像から20代の大西順子トリオの演奏、山下洋輔・渡辺香津美デュオ「クレオパトラの夢」まで、時間を忘れて見入ってしまった。
いまひとつ。本書に出てくるので、しばらくご無沙汰だったアルバムを何枚か聞いた。パウエル、ケリー、エヴァンスら今もよく聞くピアニストは別として、いちばん新鮮だったのがデューク・エリントン・トリオ『マネー・ジャングル』。ピアニストとしてのエリントンの凄さと新しさを改めて知った。著者も言うように「エリントンこそジャズ史における最初の『前衛』」だなあ。もうひとり、ニューヨークでライブを聞いたことがあり、2017年に亡くなったジェリ・アレンの「ララバイ・オブ・ザ・リーヴス」に涙した。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





