昭和の劇 映画脚本家 笠原和夫【笠原和夫・荒井晴彦・スガ秀実】
昭和の劇 映画脚本家 笠原和夫
脚本家という商売の宿命的な悲しみ
| 書籍名 | 昭和の劇 映画脚本家 笠原和夫 |
|---|---|
| 著者名 | 笠原和夫・荒井晴彦・スガ秀実 |
| 出版社 | 太田出版(608p) |
| 発刊日 | 2002.11.6 |
| 希望小売価格 | 4286円 |
| 書評日等 | - |
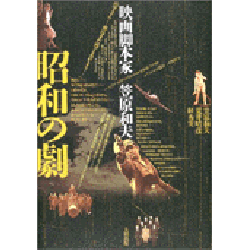
それにしても映画の脚本家というものは、つくづく因果な商売なのだと思う。
笠原和夫といえば、1960~70年代やくざ映画の傑作「博奕打ち総長賭博」や「仁義なき戦い」の脚本家として知られる。
「総長賭博」(山下耕作監督)は、何年にもわたって積み重ねられたやくざ映画の「型」の頂点を究め、そのことによって逆に「型」を超えた人間の裸の感情を露出させた作品だったし、「仁義なき戦い」(深作欣二監督)は、パターン化した「型」を打ち破って、全編手持ちキャメラの揺れうごく映像をスクリーンにたたきつけた作品だった。
「総長賭博」は全共闘運動で大学と社会が騒然としていた1968年。「仁義なき戦い」が三島由紀夫の自決や連合赤軍事件を経て閉塞感が漂っていた1973年。2本とも、映画を見終わって映画館から夜の町へ踏み出したときの叫びだしたくなるような興奮を、今でも思いだすことができる。
そんな傑作を、完成後の試写ではじめて見た脚本家は、どちらの映画にも不満で「頭にきた」のだと回想する。
「総長賭博」は、クールなドキュメント・タッチを期待していたのに「エラくのんびりしたリズム」だったし、「仁義なき戦い」の場合は、笠原は主人公に戦争による屈折から殺人へといたる影を背負わせたいのに、それ抜きにドンパチやらせ、時代性はニュース映像やナレーションで説明すればよい、というつくりになっていたからだ。
そんなふうに、脚本家と監督の思いはどうしようもなくすれ違うものらしい。これが例えば出来の悪い映画に、こんなつもりではなかったと脚本家が怒るのならわかる。でも、笠原が怒っているのが映画史に残る傑作に対してだということに、脚本家の宿命的な悲しみを感じてしまう。
すでに映画を見てしまった僕たちは、あの様式のぴたりと定まった映像でしか「総長賭博」を考えられないし、主人公の内面に錘を下ろしていったのでは「仁義なき戦い」の爆発的なスピード感は生まれてこなかったと思う。
でも、脚本家は脚本家で、頭のなかで別の映画を完成させているのだ。脚本を書きながらカット割りをし、役者にセリフを言わせ、フレームを定め、カットとカットをつなぎ、そのような作業を繰り返して頭のなかで映画を完成させる。でも、実際に現場で映画をつくるのは監督なのだ。因果な商売というしかない。
この本は、笠原が手がけた100本以上の作品に沿いながら、荒井晴彦(脚本家)、秀実(評論家)という全共闘世代の2人のインタビュアーが脚本家の積もりに積もった思いを引きだした分厚い一冊。日本映画(とりわけ東映)ファンにはたまらない。刊行直後に笠原が亡くなったこともあって、彼の墓碑銘のような本になってしまった。
笠原和夫は、昭和20年代末に東映宣伝部に入社し、美空ひばり映画で脚本家としてデビューした。映画全盛期の熱気のなかで、大衆娯楽映画をつくりながら脚本のコツを学んでいったエピソードが面白い。例えば、ひばり主演のスター映画はスクリーンに彼女のオーラをいかに華やかに咲かせるのかが勝負だ。
「ここのセリフを直せとか、ここのシーンをこう変えろとか(監督が)言ってくる。こっちは、どうしてここを変えなきゃならないのかなあと思うんだけど、そうやって直してみると、映画になったときに、ちゃんとそこでオーラを発散するんだよ。そういう意味では、やっぱり昔の監督さんはプロでしたね。要するに職人なんですよ」
あるいは、マキノ雅広の次郎長もので学んだ「アヤ」のつけかた。「アヤ」とは、人間関係の因縁やしがらみのなかでドラマをつくってゆく伝統的な作劇のやり方。長谷川伸の「沓掛時次郎」や「瞼の母」を思えばよい。というより、日本の大衆的な芝居や映画は、現在のテレビドラマに至るまで、ほとんどが「アヤ」を駆使してできている。
「それは悪くすればマンネリズムになるし、やりすぎじゃないかということになっちゃうんだけど、そのアヤの中でうまく人間性というものを表出できるのであれば、これが一番いいわけだよ」(その見事な例が「総長賭博」ではないか)
「アヤとかをなくしちゃうと、単なる日常になっちゃうんだよ。で、そういうアヤが出来すぎだとか嘘だとか思わせないためにリアリズムという手法が必要になってくるわけであってね。だから、アヤがないドラマを一所懸命撮るというのはリアリズムじゃなくて、単なる日常の模写でしかないわけだよ」(そのリアリズムの見事な例が「仁義なき戦い」ではないか)
笠原和夫はひばり映画で学び、「祇園の暗殺者」などリアルな時代劇映画で才能を認められた。やがて、東映では時代劇が行きづまり、新たな路線としてやくざ映画に活路を見いだしていく。そのときのエピソードがまた、いかにも東映らしい。
後に社長となる岡田茂(撮影所長)が、高倉健で「日本侠客伝」というシリーズを立ちあげようと笠原に話を持ってくる。笠原は考えた末にこう答える。
「黒澤さんの「七人の侍」と「仮名手本忠臣蔵」をパラダイムとして二本用意していって、岡田さんにどっちがいいかって言ったんですよ。すると「お前、どう思う?」って言うから、「大体、映画が不景気な時には忠臣蔵のほうが当たるんです」って言ったら、「じゃあ、そっちにしよう」という簡単な話でね(笑)」
「七人の侍」は世界映画史に残る飛びぬけた傑作だけれど、作品を支配する圧倒的なアクションを支えるのは、ヒューマニズムという戦後的なイデオロギーである。笠原も岡田も、そうしたモダンな、しかし一歩間違えばウソくさくなるドラマづくりを暗黙の了解として避けた。
そうか、やくざ映画は「忠臣蔵」だったのか。そういわれれば、やくざ映画前半の「がまん劇」も、ラストの「なぐり込み」も、実によくわかる。その笠原の発言の背後には、かつてシナリオ修行していたときにマキノ光男(戦前の満映から戦後の東映で活躍したマキノ一家のプロデューサー)に言われた「仮名手本忠臣蔵、円朝、松竹新喜劇を読め」という言葉がある。
笠原和夫の書く脚本は、そんな伝統的なドラマづくりの骨法を芯に、関係者・当事者への取材にもとづいてディテールを積み重ねた独特の「リアリズム」を本領とした。その頂点が「仁義なき戦い」であることは、自他共に認めるところだ。自分の「リアリズム」に耐えられる監督は山下耕作と深作欣二だと、映画の完成時には「頭にきた」二人の力量を認めてもいる。
やくざ映画以後の「二〇三高地」「大日本帝国」といった戦争・歴史映画でも、その姿勢は変わらない。僕は彼の戦争・歴史ものをほとんど見ていないので、そのあたりの判断はできない。けれど、笠原の言う「リアリズム」で貫かれたこれらの作品に、左からは右翼的、右からは左翼的と批判されたにもかかわらず、彼は堂々たる自信を持っている。
笠原の脚本は、やくざ映画にせよ、戦争映画にせよ、その素材からしてイデオロギー的な目で裁断されやすい。戦争ものなど、内容以前に映画化することそれ自体に政治的な批判があった。でも、彼の脚本を読み、その発言に耳をかたむけていると、その背後にはイデオロギーでは割りきれない、ある感情が横たわっているのに気づく。それを笠原は「陶酔」と名づけている。
「日本暗殺秘録」のラストをどうするかで、笠原と監督の中島貞夫のあいだで意見が食い違った。そのことに関して、笠原はこんな発言をしている。
「中島は、全共闘みたいなことでラストに(左翼的な)理屈をつけようとするでしょ。僕は違うんだよ。僕は陶酔というものを描きたかったんだよ。それでラストは、テロリストの陶酔というものが、最後にこういう形になっていくんだというものを見せようと。……「仁義なき戦い」でもそうなんだけど、僕は答えが出ない映像をやりたいわけですよ」
笠原が「陶酔」と呼び、あるいは「答えが出ない映像」と呼ぶものは、映像そのものが本来的に持っている生命力のことに違いない。映像は、どのような文脈のなかに置かれるかによってイデオロギーの言葉ともなりうるが、そのような意味を超えて見る者に迫る映像の原初の力。笠原は彼の書く脚本のなかで、一貫してその力を追いもとめた。
彼はこの本に収録されたエッセイで、同じく「陶酔」という言葉を使って、戦時下のこんな体験を記している。
「敵の爆撃機が超低空で頭上を飛び交い、視界一面が炎で染まった光景は、壮観でさえあり、痺れるような陶酔に浸った。直撃弾を受けた級友二人が即死して、その脳奬と鮮血が飛び散った中に立ったとき、自分が神になったかと思うほど勇気が充ちた。それは、歓びとも言えるほどの昂揚であった」
大衆的なエンタテインメントであり産業でもあるという条件のなかで、そんな原風景を映像化することにこだわり、しかもそれを生涯にわたって持続させた笠原は、映画と、しかも東映という会社と、幸福に出会ったのだと思う。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





