絶筆【野坂昭如】
絶筆
| 書籍名 | 絶筆 |
|---|---|
| 著者名 | 野坂昭如 |
| 出版社 | 新潮社(379p) |
| 発刊日 | 2016.01.22 |
| 希望小売価格 | 1,728円 |
| 書評日 | 2016.02.18 |
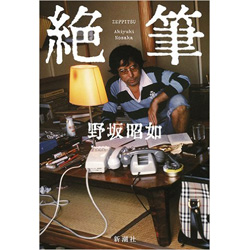
野坂昭如は2015年12月9日に85才の生涯を閉じた。それに先立つ2003年5月に脳梗塞を発症したものの、陽子夫人の手を借り口述筆記によって文章を発表し続けていた。本書も2004年から雑誌「新潮」や「新潮45」に掲載されていた日記形式のコラムをまとめたものである。タイトル「絶筆」とあるように最期のコラムは死亡当日のもので死の数時間前の口述と書かれている。
十年を超える、リハビリの中の記録だけに、毎日の食事や日常生活描写が多くなっているのは当然として、以前からの趣味であるラグビーや相撲といったスポーツ、過去の戦争の記憶、政治状況に対する思いなどが広範囲に綴られていて、その旺盛な好奇心や過去の記憶も衰えることのない姿は野坂の強さを表していると言える。加えて、第二次大戦に関する記憶に基づく戦争への警鐘が常に底流としてあるが、一方、「思い出」として穏やかに語られる部分もある。
それは戦後70年という時間の経過のなせる業なのか、もしくは、野坂自身がその余命を意識した結果なのかは判らない。ただ、読み手としてはホッと出来る部分でもある。この十二年間の口述日記を通読すると、日々の記述は個別的・断片的であるものの、そこには自らの人生を振り返えるという思考パターンがあり、彼が生きてきた時代を意識しつつ、その時代にどう向き合ってきたのかを示している。それは破天荒や無頼を看板としながらも、この口述を通して妻と娘に対する感謝の気持ちが極めてシャイな言い回しではあるものの、語られていることが印象深い。
野坂昭如の名が世間に知られた契機が、1960年代初頭の「プレイボーイ入門」や「エロ事師たち」といった本だとすると、高校生になりたての我々の世代は野坂のデビューを体感している世代と言える。大橋巨泉、野末陳平、寺山修司、大島渚、といった人物たちが、月刊誌から週刊誌に、ラジオからテレビにメディアが変化して行く中で新しい文化を創り上げつつあった時代だ。
この時期に多感な高校生として興味と憧れをいだきながら彼らの活躍を見ていた事も懐かしい。戦争を戦った我々の親の世代から見れば嘆かわしい風潮と見ていたに違いない。たしかに、野坂の社会への登場の仕方は、サングラスを掛けて酒と女を語るいかがわしさ満載の姿を演出していたし、メディアもそれをはやし立てていた。本書では、「プレイボーイ」というキャッチフレーズを野坂につけたのは、雑誌「銀座百点」で吉行淳之介との対談が掲載された時であり、自らが名乗ったものではないといっている。しかし、「遊び人」を総称する「プレイボーイ」という言葉を冠せられた野坂はしっかりと世の中の流れに乗り、風を捉えるというしたたかさを持って生きていたと思う。
その後も「無頼派」と呼ばれたり、自ら「焼跡やみ市派」と称して、時代の中の立ち位置と歴史観を鮮明にしていく。そうした野坂の仲間である文壇、映画人、演劇人たちが銀座を根城に飲み、歌い、語り、喧嘩した状況が本書でも表現されている。その「無頼派」としての真骨頂が時を経て突如報道されたのが、大島渚と野坂の殴り合い事件である。1990年、大島渚と小山明子の結婚30周年を祝うパーティーが行われた時、大島が祝辞の順番を間違えたことから、腹を立てた野坂が祝辞を述べた後、檀上で大島にパンチを浴びせ、大島も野坂をマイクで殴りつけるという騒ぎだ。2013年1月に大島渚死去とのテレビニュースが流れた時の感想。
「ぼくと大島が映っている。彼の訃報と、このシーンがセットになっているようだ。恥ずかしい。申し訳なかったというより、懐かしい思い。そして、少しおかしい。不謹慎ながら笑う。……30才を過ぎたあたりからのつき合い。ジャンルは違うが、お互い周辺を蹴飛ばしてきた者同士。今の60代、お前らに殴り合う相手は居るか。ぼくにはいた」
ある時はスタイリッシュに登場し、遊び人として生き、そして「無頼派」を名乗り、開き直って戦後を生きてきた野坂は、その根底に戦争を知っている世代、換言すれば戦争で多くの物を失った世代であり、被害者ゆえの戦争否定の考えを貫いていた。2015年の6月5日のコラムは「70年前の今日、ぼくは神戸で焼け出された」という文章で始まっている。この空襲で養父を失い、その数か月後には妹を栄養失調で失ったことに対する思い出が綴られている。
まさに、失ったものの大きさを忘れることが出来なかった人生なのだろう。戦争は彼にとって人生そのものであっただけに体験が全てである。直木賞をとった「火垂るの墓」や「アメリカひじき」、「1945・夏・神戸」などの作品をはじめとして多くの敗戦体験文学を残しているのだが、「沖縄」と「原爆」と「引き揚げ者」は題材にしなかった。書かなかったのではなく、書けなかったと語っている。20万人の戦死者を出した沖縄戦の、地形を変えたと言われるほどの艦砲射撃をとても想像できないというのがその理由である。
それだけに、こうした時代を生き抜いた野坂は「少しでも戦争を知る人間は戦争について語り伝える義務を持つ……戦争は醜い。僕の中に戦争の記憶は如何ともしがたく骨身に絡んでいる」と語ると同時に、「かって国民より国家を重んじ、日本国民は戦争に巻き込まれた。……国民は自国のお上の下心を疑い、矛盾を追求した方がいい」と現在の政治状況、特に憲法改正と集団的自衛権については執拗に語り続けている。
このように野坂の人生は「失った10代」だったと言える。それだけに、本を読みたいとき(10代後半)が戦後すぐの物資欠乏の時代であり、国としても国民が生きることに精いっぱいで、知的欲求を満たす書籍にまで資源を回すゆとりは無かった。だからこそ、野坂はこう述懐している。
「本を読んで血肉になるのは十代のうち、二・三十代は所詮うわっ面、見栄と誤魔化しに過ぎない。その後は寝て起きると忘れてしまう」
確かに十代は正しく吸収しているかどうかは別として、興味ある分野の本を読む楽しさを身に付ける時代である。血肉になる時代を逃してしまった世代だからこその感覚だろう。
口述を筆記してくれているのは陽子夫人なのだが、多分野坂は自らの身体が思うように動かないことによるもどかしさを表情や言葉に出していたはずだ。脳梗塞のリハビリの回復期は発症後一年ぐらいで、以降は維持の期間に突入する。だからこそ患者にとってはきついリハビリになるし、否が応でも死について考えることになるが、「医学の進歩は死ぬべき人を死なせない。病院は末期の患者に対し延命を行う。人間の自然な姿ではない」との野坂の言葉も観念ではなく、実感なのだろう。
うつむいて歩けば桜盛りなり 野坂昭如(2009年)
本書から野坂の85年間の生き様を間接的でも振り返ることが出来る。しかし、エッと驚くような新しい発見が有るわけではない。そうだよな、という納得感が感想として残る。2015年12月9日の最期の文章。
「あせらない。あせらないと妻が呪文のように唱えているが、ぼくはちっともあせっちゃいません。さて、もう少し寝るか。この国に、戦前がひたひたと迫っていることは確かだろう」
高校生の頃から50年以上前からの読者だった自分としては、もう少し語らせたかったと思う気持ちと、お疲れさまという気持ちが交錯する。( 内池正名 )
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





