贖罪の街(上下)【マイクル・コナリー】
贖罪の街(上下)
| 書籍名 | 贖罪の街(上下) |
|---|---|
| 著者名 | マイクル・コナリー |
| 出版社 | 講談社文庫(上320・下320p) |
| 発刊日 | 2018.12.14 |
| 希望小売価格 | 各950円 |
| 書評日 | 2019.03.15 |
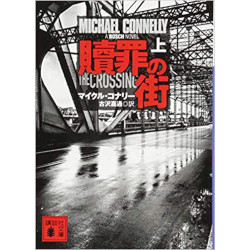
ミステリーのシリーズものを読む楽しみは、なじみのバーで酒を飲むのに似ている。バーへの道筋の風景は、すっかりなじんでいる。扉を開け、まずはお気に入りの席が空いているかどうか目で確かめる。その席に座ると、バーテンダーが黙っていても自分のボトルをカウンターに置いてくれる。いつもの酒(ジャック・ダニエルズのソーダ割)が目の前に差し出される。そして気の置けない会話。すべての手順が決まりきって、すべてが心地よい。
ミステリーのシリーズものを読むのも、そんな安心感とともにある。なじみの主人公と、主人公を取りまく常連たち。彼らの関係性が時に発展し、時に停滞しながらも小宇宙をつくりだし、そのなかに浸るのが快い。でも読者というのは贅沢であり残酷でもあるから、長いことシリーズものを読んでいると、ある瞬間、その小宇宙になじみがあるからこそ飽きがくることがある。そんなふうにして、いくつのシリーズものと別れてきたことだろう。
ローレンス・ブロックの探偵マット・スカダーものは飽きがくるまえにシリーズ自体終わってしまったが、ロバート・パーカーのスペンサー・シリーズ、パトリシア・コーンウェルの検視官スカーペッタ・シリーズ……。ほかにもある。そんななかで、今も読みつづけているのがマイクル・コナリーの刑事ハリー・ボッシュ・シリーズだ。『贖罪の街』は、その最新作。
実はボッシュ・シリーズの前作『ブラックボックス』や前々作『転落の街』あたりで、少しだけ飽きの兆候を感じていた。このシリーズでは、ボッシュの相棒や恋人はたいてい一作、あるいは数作で関係が終わるよう設定され、常連にならないよう周到に配慮されているが、元妻との間に娘がいて、その娘がボッシュと同居する展開になってきた。年頃の娘は父親に反発しつつも、捜査官という仕事に興味を持っている。
また、コナリーの別シリーズにリンカーン弁護士もの(弁護士ハラ―)があるが、リンカーン弁護士シリーズのなかにボッシュがときどき登場するようになり、あまつさえボッシュと弁護士ハラ―が異母兄弟であるという、あまりリアリティを感じさせない関係が設定された。ボッシュ・シリーズの本書では、逆に弁護士ハラ―がはじめて登場する。娘やハラ―といった常連登場者とボッシュが織りなす「なじみの世界」は、やがて飽きの原因になるのでは。そんな危惧を持ちながら読みはじめたのだった。
そしてその不安は見事に裏切られた。ボッシュ・シリーズのなかでも屈指の面白さになっている、と思う。この作品でのボッシュは、ロス市警を退職し刑事という肩書を持たない、ただの男。物語は、ロス市高級公務員の女性が自宅で乱暴され撲殺されたことに始まる。被害者の身体に残されたDNAから、元ギャングで今は更生し画家になっている男が逮捕される。画家は、かつて弁護してくれたハラ―に冤罪だと訴える。冤罪を確信したハラ―は異母兄ボッシュに、弁護士である自分の調査員になって事件を調査してほしいと頼みこむ。
裁判では検察と一体になる警察官が、逆に弁護側の調査員になる。警察の側から見ればこれは許されない裏切り行為となる。ボッシュはハラ―に言う。
「殺人事件捜査で弁護側につく捜査員がなんと呼ばれているのか知っているか? ジェーン・フォンダと呼ばれるんだ。彼女が北ベトナムと誼を通じたとして非難されたように。わかるか? ダークサイドへ渡った(クロッシング──本書の原題)ことになるんだ」
ジェーン・フォンダの名前がいまだにこんなふうに使われているのに驚くが、それはともかく、退職したとはいえ精神は刑事のままであり、警察に仲間もたくさんいるボッシュにとって、異母弟の頼みを聞いて「ダークサイドへ渡る」ことには心理的に大きな抵抗がある。とはいえ、ハラ―がボッシュに事件の調書を手渡し、ボッシュがそれを読み始めると否応なく刑事としての勘が働きだし、調書の小さな疑問点を見つけだしてしまう。
結局、ボッシュはハラ―の調査員として働くことを決心する。元の仲間からは「がっかりした」という電話が何本もかかってくる。ボッシュは、冤罪であるなら真犯人が大手を振って街を歩いているはずだ、それを見つけだす仕事は刑事と同じだ、と自らに言い聞かせる。ボッシュとハラ―の異母兄弟という設定が、シリーズものの安定した「なじみの小宇宙」を生むのでなく、逆に緊張と葛藤を生みだす。以後、ボッシュのさまざまな場面での葛藤が、この物語を駆動するエンジンとなっていく。
「羞恥の思いに首のうしろが火照るような気がした。自分よりまえに引退し、次に消息を知ったときには、刑事弁護士のために働いていたり、あまつさえ公選弁護人事務所のために働いていたりした連中全員のことを思い浮かべた。ボッシュは彼らが犯罪者そのものであるかのように彼らとの付き合いを絶った。だれかが通路を越えたと聞いた瞬間、ボッシュはその相手を受け入れがたい人物(ペルソナ・ノン・グラータ)と見なしたのだ。それなのに、いま……。ボッシュは舌を火傷させるほど熱いコーヒーに口をつけ、いま感じている不快感を脇へどけようとした」
もともとボッシュはベトナム帰還兵という設定で、地下に張り巡らされたベトコンの地下トンネルで戦友の死体を発見したときの恐怖と不安が、刑事になってからもたびたび悪夢として蘇ってくる。その恐怖と不安が、時に捜査している事件の犯人の恐怖と不安にシンクロし、事件解決のヒントとなるようなこともあった。そのように心に黒い塊を抱えこんだ刑事として設定され(ヒエロニムス・ボッシュという奇想の画家と同名というのも、彼の精神のあり方を暗示している)、強面と不安な魂が同居する孤独な男としての個性がシリーズを牽引してきた。それがこの作品でも引き継がれているのが嬉しい。
もうひとりの常連で、「なじみの関係」である娘についてもうまく処理されている。物語の終盤で真犯人がボッシュの自宅を襲う場面があり、ひとり自宅にいた娘が危機に陥るというのがありがちな設定だけれど、この事件の間、娘は学校のキャンプに出かけて自宅にいないことになっている。
ともあれ、ボッシュが相手に刑事と思わせる犯罪すれすれのやり方で調査を進め、鉄壁と思われたDNAの証拠を突き崩して真犯人をあぶりだし、最後に法廷でハラ―が逆転無罪を勝ちとるまでのストーリーテリングのうまさには、いつもながら舌を巻く。ジャズ好きのボッシュが自宅でジャズを聞くシーンがどの作品にも出てくるけれど、ここではクライマックスにウィントン・マルサリスが流れている。そのことでボッシュは命を救われる。「もし、ウィントンに会うことがあれば、礼を言っておくよ」と、ボッシュの軽口。シリーズ健在を確認した。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





