戦争の思想史【中山 元】
戦争の思想史
| 書籍名 | 戦争の思想史 |
|---|---|
| 著者名 | 中山 元 |
| 出版社 | 平凡社(336p) |
| 発刊日 | 2025.02.26 |
| 希望小売価格 | 3,300円 |
| 書評日 | 2025.07.18 |
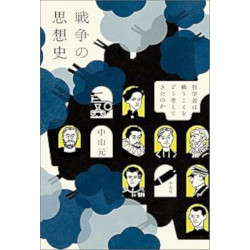
著者は哲学を専門とし著作・翻訳も幅広く出している。本書ではアリストテレスを始めとして歴史に残る多くの哲学者、思想家、宗教家たちが古代からの戦争について語って来た言葉を戦争の実態を振り返りつつ紹介している。
ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ攻撃など東欧・中東地域の戦闘のニュースが日々飛び交う中、住民たちの被害の映像を目にするにつけ、戦いの理由に関わらず悲惨さに心が痛む。世界規模の和平確保の仕組みとして国連も機能しなくなっているということを痛感する。
1947年(昭和22年)生まれの私は実態的な戦争体験は皆無である。ベトナム戦争も同時多発テロ事件も臨場感を持って記憶しているものの映像からの間接的体感でしかない。しかし、本書でも述べられている様に、人類の歴史は戦争の歴史であり、それは現在も変わらない。著者は「平和とは戦争の中断した短い間のようなものに過ぎない。その短い平和の時期においても自然災害などが発生することを考えると、人間にとって平和とは本当に限られた『時』であると思わざるを得ない」という感覚は納得ができる。現代の日本人としては自然災害をいろいろ体験してきているものの、戦争となると実感の乏しい戦後80年を過ごしている。そんな中で本書の根幹は「人類はなぜ戦争を止められない歴史を繰り返してきたのか」という問いかけである。古代、中世、近代、現代という時間軸で時代毎の戦争においてその戦いをどう正当化してきたのかを考察している。今更ながら、中学・高校で世界史を勉強したつもりになっていても、それは年号と事象の断片の暗記作業だったかを痛感しながらの読書となった。膨大な歴史の中で、いくつかの気付きをメモしてみた。
考古学的に戦争証拠が確認出来る最古の遺跡は一万年前にヨルダン渓谷のエリコにつくられた農業主体の定住型集落で、狩猟民族からの襲撃に備えて高さ4mの壁で集落全体を囲っている。こうした集落が統合していくのが国家形成の始まりと言われている。
過去の伝統的な戦争論は国家間の争いに絞って語られていることが多いが、国家形成以前からの戦争を考えるためには著者は文化人類学的な戦争定義で考えることを提案している。それは「異なる政治的統合を持つ集団間における政治的武力衝突」として「戦争」「紛争」「略奪」「殺戮」といった事象を含め、「国家・集団」とは切り離されてはいるものの、お互い影響し合う概念とみている。
中世に入り、ローマ帝国はキリスト教を国教と定め、「異教徒からキリスト教を守る」という考えのもとエルサレムを解放する目的で十字軍による戦いが始まる。こうしてヨーロッパは英・仏の百年戦争をはじめとして、ヨーロッパ内に止まらず植民地を含めた戦争を繰り返すことになる。この時代の戦い方の変化は大きく、それまでは城塞を攻める戦略は兵糧攻めのように日数のかかるものだったが、大砲の発明により城塞を短期間で破壊することが可能になった。また槍を持った騎兵による軍隊から、銃の発明で歩兵中心の戦いになり、軍隊規模が拡大した。
また、イギリス・フランス・オランダ・スベインなど君主と資本家との協力関係が成立し、海外を含めた市場での事業のために軍事的な保護の必要性とともに、経済活動による税収で常備軍の維持が可能になった。イギリスの経済学者アダム・スミス(18世紀)は「貿易により国内産業の分業や生産性向上を目指す」という貿易経済的側面と同時に「自国を他国の暴力から守るための軍事力は必要。近代の戦争は火器の発明等で経費が掛かるようになってきて、まずしい国は戦争を仕掛けられなくなった。火器の発明は一見極めて危険と思えるが、文明の永続の為には有利」としている。まさに大国主義そのものの考えが提示されている。
一方、ドイツ哲学者のカント(18世紀)は「永遠の平和のために」という論文で「常備軍の廃止、敵対行動の禁止等とともに国家が自ら選択した国家法(憲法)が必要であること。各国が互いに主張することの正邪を判断するための国際法やさまざまな言語と宗教の違いが戦争の口実を与える一方、文化を向上させ、お互いに平和な状態で理解を深め合う力を発揮する場として国際的な国家同盟が必要」と提案するなど、「戦争の正義」についての議論も深まって行くがあくまで文明国間の議論であった。文明国と未開の民族の間での非対称の戦いを想定しているわけではない。銃で武装したヨーロッパ兵とアメリカ・インデアンの戦いは単なる「人狩り」としか言いようがない戦いないのである。
近代の戦争はフランス革命がトリガーとなり、第一次世界大戦へと進んで行く。フランス革命も当初のフランス国内の事件から、ナポレオンの登場とともに革命の防衛という使命を越えてヨーロッパ各国を巻き込んでいく。そして、ナポレオンが皇帝に即位して王政を復活させたことで、フランスの思想家のシモーヌ・ヴェイユが「武器を持った市民が真の意味で自由を目指す戦いはパリコミューンだけだった」と語っているのも歴史の皮肉としか言いようがない。
ドイツ哲学者ヘーゲル(18世紀)は「戦争は外から偶然にやってくるものではなく、国家として必要な要素。長く風が吹かないと海が腐敗するように、長い平和は国民を腐敗させる。平和は目指すべき理想であり、戦争は平和を実現する力を持つ」と語るのもナポレオン体制の腐敗を想定していたのかとも思う。
ナポレオン一世の後は絶対主義国家が復活して抑圧的な体制となり、ヨーロッパ各国ではその体制打破を目指した社会革命運動とナショナリズムが結びつき民族自決と独立運動が盛り上がる。ロシア革命(1905)に進んで行く。
第一次大戦(1914~)はドイツ・イタリア・オーストリアの三国同盟とイギリス・フランス・ロシアといった連合国との戦いとなり、総動員体制が敷かれたことで「総力戦で銃後の人間まで巻き込まれ、死に直面したことで大きな幻滅が生まれた」とフロイトの言葉となる。
第二次世界大戦(1939~)では総動員体制はさらに強化されるとともに植民地からも動員して超国家的な戦争となり、一国家では戦争をするには小さすぎる単位になったことから、国家主権の重要性は失われていく。ヒットラーはラッツェル(ドイツ地政学者)の考えを踏まえて、「国民の成長とともに国家の規模も拡大しなければならず、そのために隣国との戦いと併合は必要」としてオーストリア・ポーランドの併合を行う。
フランスの哲学者バタイユはファシズムについて「資本者階級と労働者階級ともに生産と蓄積という意味では同一性を持っている。しかし、異質なものは無意識のうちに排除していく。社会の上部で異質とされた人間と下部で排除された人間同士で手を握った結果、ファシズムが生まれる」としている。この言葉を読んでいると、なにやら現代のトランプと白人労働者の結託というアメリカを想起してしまう。
ファシズムとの戦いはヨーロッパ戦線にアメリカとソ連が参戦することで決着した。大戦後の世界はこの遅れて参戦した二つの国が中心となって廻って行く。アメリカは「原爆」の技術を持ち、ソ連はミサイル技術で優位に立っていた。この二つの最終兵器による「恐怖の均衡」が冷戦に向かわせる。
新しい戦争の時代は1989年のベルリンの壁の崩壊により冷戦が終結したときから始まり、2001年9月11日に米国多発テロが起きた。非対称戦争の典型で、テロリスト側は米国の民間航空機をハイジャックして自爆攻撃を仕掛けることで、大国が保有する技術をテロリストも利用可能なことを見せつけた。
スロベニアの思想家ジジェクは「文明化された西洋社会は繁栄と平和を享受してきたが、これは暴力と破壊を国外に転出することで保たれていた。今回のテロ攻撃の効果は現実的なものというより象徴的なものと考えるべきだ。・・・現実の砂漠にようこそ」と先進国諸国に覚醒を促している。
2023年10月7日ハマスはイスラエルに侵攻して数百人の人質を拉致した。イスラエルは直ちにガザへのジェノサイドともいえる攻撃に世界から非難の声が挙がったが例外はアメリカとドイツであり、ショルツ首相は「イスラエルと国民の安全はドイツの国是」と言い切る。アメリカの政治学者ナンシー・フレイザーは「人間の尊厳の原則は全ての人に等しく適用されなければならない」と語り、ショルツの言動に反対したところ、彼女はドイツのケルン大学教授に招聘されていたがこの発言で取り消されたと言う。
ロシアとウクライナ、イスラエルとガザ・イランの二つの戦いはともに核保有国と非核保有国の非対称の戦いである。こうした戦いはこれからの戦争の典型になる「古くて新しい戦争」と著者は見ている。地政学的有利な土地、宗教・文化、民族、天然資源など戦いの種はいくらでもある。「戦い」を「競争」としてお互い切磋琢磨するとか「共創」という協力の世界が望まれる。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





