アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?【カトリーン・マルサル】
アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?
| 書籍名 | アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? |
|---|---|
| 著者名 | カトリーン・マルサル |
| 出版社 | 河出書房新社(288p) |
| 発刊日 | 2021.11.16 |
| 希望小売価格 | 2,310円 |
| 書評日 | 2022.03.17 |
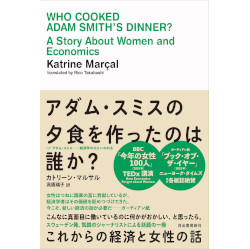
著者のカトリーン・マルサルは1983年生まれのスウェーデン出身のジャーナリスト。特に経済、女性問題について発言してきた女性。原書は「Who cooked Adam Smith’s dinner?」と題され2015年の刊行。30才そこそこで本書を世に問うたと考えると大胆な発想と切り込んでいくパワーにも納得がいく。
アダム・スミスに始まる経済学は「国富論」(1776)に代表されるように、国民一人一人の利益追求が国の全体効率に繋がるという考えで、それを支えるのは「Invisible Hand(見えざる手)」という自然均衡概念である。それを簡潔に示した例として本書のタイトルにもなっている話は、「我々が食事を手に入れられるのは、肉屋や酒屋やパン屋の善意のお陰ではなく、逆にいえば対価をもってそれらを手に入れるのも利己心があるからだ」というもの。この言葉に対して著者は「アダム・スミスは食べている肉を焼いてくれた人を見落としている」と鋭いツッコミをいれているのだ。経済循環を考えた時に肉屋と食べる人を繋ぐ部分、いわゆる「家事」全般はアダム・スミス以降の経済学でも視野に入れられることがなかった。利益を求めない貢献、子供を生む、子供を育てる、家族の食事を作るといった活動は経済の視点からは無視されるということであり、国家のGDPに含まれることもない。こうした点を経済学の不十分さとして著者は論じている。
経済活動を考える際に、人の行動をモデル化するために過去からいろいろな例が示されて来た。その一つがロビンソン・クルーソーである。無人島に流れ着き、ルールも法律もない純粋な自己利益だけで生活し、制約は時間と資源の量だけ。彼は生産者でもあるとともに消費者だから、物の価値は需要と供給によって純粋に決定される。このように経済モデルは理想(欲望)を目指し有限な資源の配分を選ぶことで「調和と均衡」が図られる。そこに「善意」も「愛」も入る余地はない。まさに著者が非難する、伝統的な経済学の世界であることは間違いない。こうした状況を変革しようと挑戦した女性としてナイチンゲールを取り上げている。ナイチンゲールはクリミア戦争(1853)の時イギリスから38名のボランティアとともに黒海に向かい、野戦病院で看護活動を通して兵士の死亡率を大幅に引き下げた。その詳細な活動記録を残したうえで、統計学者でもあった彼女は統計データを駆使して看護のあり方や看護師に対する待遇改善を政府に求め続けた。しかし、社会はそのナイチンゲールを「白衣の天使として、男性が必要とする女性の形に歪めて行った」という見方をしている。ここでも「愛情」や「ケア」は賞賛されたものの、社会を変革するには至らなかった。
19世紀、20世紀と社会の豊かさは手にしてきたものの、貧困を無くすより格差を広げたというのが著者のもう一つの主要な指摘。そうした格差が隠されてしまう仕組みの一つがGDPの算定の仕方だ。同じ種類の労働でもGDPに含まれたり含まれなかったりすることがある。「男性が雇っている家政婦と結婚すると、GDPが減る」とか、「高齢の母親を老人ホームに入れるとGDPは増加する」といったケースだ。ただ、依然として家庭内の無償労働についてカナダの推計ではGDPの40%程度が隠れているという数字を聞くと、いささか驚かされるとともに、人間の活動成果として測定する手段の必要性は理解出来る。
また、男女間の所得格差を提起している。第二次大戦後、女性の平等が叫ばれる中で、「女性は自由で孤独で競争心の強い人間になれる」と言われ始めるが、経済の観点で言えば「女性は家事をしなければならず疲れることで、仕事の効率が下がるとともに、時間の制約もあるので低い賃金となる」とか、逆に「女性は賃金が安いので家事をやらざるを得ない、男女どちらかが家事をするなら賃金の安い女性にやらせた方が損失は少ない」といった堂々巡りが続いた。しかし、考えてみれば「髪結いの亭主」ではないが、女房の方の賃金が高ければ、男は家事に専念できる。そう考えると男女の二元論ではなく、人によると思うのだが、例外的事例でしかないのも事実。
20世紀に入り、女性は相続権、就職、借金、同一賃金など、様々なジェンダー間の平等な権利を手に入れようと活動してきたが、一方、競争を前提とする社会に進出した女性の前に立ちはだかったのは、男を前提とした社会規範であり、それにより女性は男と女の双方の規範を負担する必要が現実であり、男はありのままの自由を認められていても、女はありのままの自由は得られていないという。要すれば男社会に女を混ぜ込んだだけでは平等は達成されないという見方だ。ただ、第二次大戦後、ボーヴォワールが唱えた女性解放思想の代表作「第二の性」というタイトルにも「何故、女性は第二?」という意見を述べているが、そこまで言わなくてもという気もする。
これだけ歴史を積み重ねてきた経済学は何故リーマンショックを予測出来なかったのか。
そして、「経済学は抽象的な架空の条件ばかり分析していて、目の前の大事な問に向き合っていない。自然の恵みを利用して人々が必要を満たし、人生の喜びを享受するやり方を研究する科学であってほしい」と著者は問い掛けている。しかし、生身の人間は常に「合理的」で「利己的」に行動するわけではない。実際の人々はいろいろな予測結果やメディアの情報に左右されながら行動する。単純化された理論上の経済人は本当の人間と違うのは当たり前のことで、本当の人間は良く言えば複雑、別の言い方をすれば非合理的な動きをする。社会活動の全てを予測することは不可能であり、社会科学の限界として理解しておくべきだと思う。
本書を読みながら、学生時代の教科書アダム・スミスの「国富論」、ケインズの「雇用・利子および貨幣の一般理論」、サミュエルソンの「経済学」、マルクスの「資本論」などが思い出された。あくまでそれらの著作には学問として接してきた限界からだろうか、著者のような読み方をしていなかった自分に気付かされる点も多かった。また、それも時代の為せる業だろうか。一方、実際の金融市場で活動する投資家たちが数字に踊らされている場面に直面したことが有る。15年程前、上場会社の経営に係わっていた時、或る女性の株主から「御社の株価動向についての見解は」といった質問に受け答えしていた。すると彼女の最後の質問は「ところでこの会社は、何をしてる会社?」と聞かれて驚いたことがある。この株主は「株価」と「その推移」だけに興味が有り、社員たちが苦労して何を作っているかとか、どんな商品・サービスでお客様から評価されているかなどは一切関心がない様子だった。そして、株価が上がれば利ザヤ稼ぎで株は売るのだろう。しかし、こうした株主も資本主義を支える投資家の一人ではあるのだが。
「男」として普段気にしていない観点がいろいろ出て来た。そうした意味では新たな発見があり、時として納得の出来ない部分もありつつ、楽しく読み終えた。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





