松本清張の昭和史【保阪正康】
松本清張の昭和史
| 書籍名 | 松本清張の昭和史 |
|---|---|
| 著者名 | 保阪正康 |
| 出版社 | 中央公論新社(320p) |
| 発刊日 | 2024.02.21 |
| 希望小売価格 | 2,420円 |
| 書評日 | 2024.05.17 |
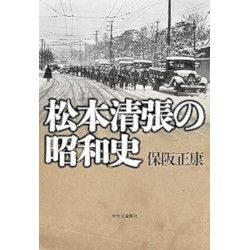
松本清張は1909年(明治42年)生まれ、高等小学校を卒業して15才で給仕の仕事に就いたのち、朝日新聞で働き始め1943年に徴兵で衛生兵として従軍。終戦後、朝日新聞に復職して40才から小説を書き始めるという遅咲きの作家である。1953年44才の時「或る小倉日記伝」で芥川賞を受賞し、「点と線」「ゼロの焦点」といったいわゆる「社会派推理小説」で一世を風靡して行く。
一方、本書の著者保阪正康は1939年生まれのノンフィクション作家として昭和史に関する著作も多く、松本より一世代若い目線から、小説とは別領域の「昭和史発掘」(週刊文春・1964年)と「日本の黒い霧」(月刊文藝春秋・1960年)に焦点を当てて松本清張の昭和史観を掘り下げている。
「昭和史発掘」は週刊文春に1964年から延べ7年という長期間連載された。取り上げられている20の事件・事象は大正末期の「大逆事件」を始めとし、「芥川龍之介の死」から「満州某重大事件」等と続き、最後に「二・二六事件」について多くの誌面を割いて締めくくっている。松本はこの時代の自身について「私は小学校卒で、かなり情けない差別待遇を受けてきた。しかし、自分で恥ずかしいと思ったことは無い。たまたま、貧乏な家庭だったので上級学校に行けなかった。・・・兵役の中でも、新兵の平等が奇妙な生きがいを私に持たせてくれた。兵役生活は人間抹殺という人も多いが、私は逆の実感を持った」と語っている。こうした経歴や生活感覚は庶民そのもので作家活動につながる要素もなく、自分の周りに起こる事柄を幾分シニカルな目で見つめている。そんな「底辺からの視線」が松本のリアリズムの原点と保阪は指摘している。
こうした人生であればこそ、松本は「佐分利公使の怪死」「小林多喜二の死」「天皇機関説」といった、集団国家の中で個人として戦った人間を敢えて取り上げているのだろう。特に、美濃部達吉の貴族院での演説全文を掲載しているのも、権力に抗する人間を詳細に読者に伝えようとする姿勢そのものだ。
加えて、保阪は現在松本清張没後30年を経てノンフィクションの分野において、今日的視点で見ても先駆的な意味を持っている点を次の様に指摘している。一つは、松本が大正末期のプレ昭和期から始まる昭和前期の重要性に注目している点。そして、二つ目は、記録の観点で事件・事象に関係する人々の自伝・回顧録・評伝にはじまり、膨大な関係者に対する取材を徹底して行っている点である。こうした多様なアブローチこそ当時のアカデミズムとの違いであり、特に二・二六事件では「当事者への聞き取りとともに、反乱側だけでなく鎮圧側の記録も多く引用している。また、上層部からの目線だけでなく、下士官150名への取材も行っている」ことを強調している。
二・二六事件を「結果」として見た場合、原因は軍内部の暗闘や五・一五事件などが「昭和史発掘」で語られている。しかし、二・二六事件を「原因」として考えた場合の以降の歴史を松本は語っておらず、ただ「日本の敗戦に直接結びついている」という言葉で終わっている点について、二・二六事件と敗戦までの6年間の「因果」についての検証もまだまだ必要ではないかという保阪の意見ももっともである。
また、松本は天皇制については殆ど語っていないのだが、「天皇制のとどめは、その国家体制に益する場合のみ天皇個人の神権の絶対性が発揮される、それに反した場合は二・二六事件のように封じ込められる。・・・そして、二・二六事件の反乱軍将校に憤激した天皇も、その後は軍部の妖怪の前に無力化した。」という記述を残している。こうした、松本の考え方については、多くの反論もあったようだが、二・二六事件を書いた理由として「これからの日本の行く道に一つの警告の意味」として「昭和史発掘」をまとめている。
「日本の黒い霧」は月刊文藝春秋1960年1月号から12月号までの一年間連載された。松本は51才、敗戦から15年が経過した時期である。そして「日本の黒い霧」においては冒頭の下山事件に始まり、帝銀事件、公職追放・レッドパージ等が取り上げられている。
対象となっている昭和中期とは、昭和20年8月15日のポツダム宣言受諾から、昭和27年4月28日のサンフランシスコ講和条約発効までの6年8ヶ月にわたる連合国の占領期間である。この時代の前半は民主化・非軍事化政策を進めアメリカ型民主主義を日本に定着させようとしていた時期であり、後半は東西冷戦が進み、日本を西側の橋頭堡と位置付けていく時期と松本は見ている。また、GHQ(連合国総司令部)内の二つの勢力の主導権争いがあったことも前半・後半分離の一因となっている。前半を担ったのはGS(民生局)でニューディラーが軍政を解体して民主化を進めた部署。後半は参謀第二部(G2)と呼ばれマッカーサー側近の軍人が多く、徹底した反共政策を進めた部署である。この勢力転換期の昭和24年には下山事件、三鷹事件、松川事件といったいずれも国鉄に関連した事件が起こる。
下山事件は当時の国鉄総裁の下山定則が公用車で出勤途中に行方不明になり、常磐線北千住の線路上で轢死体で見つかった事件。自殺か他殺かについても東大は死後轢断、慶應大医学部は生体轢断と判断が分かれた。また、警視庁捜査一課は自殺、二課は他殺を主張した。こうした中で捜査は途中で打ち切られ、現在に至るまで未解決事件のままである。松本はこの事件はGHQ謀略による他殺とみているのだ。結果論として保阪は、国鉄労使闘争に代表される、行き過ぎた民主化や共産勢力を制することで国鉄の大整理も進行していったと考えると下山の死は「徒死」ではなかったとしているが、事件の真実は依然として判っていない。
「日本の黒い霧」で取り上げた占領期の各事件について、松本はアメリカの謀略として見ているが、「日本の黒い霧」が書かれた後に判明した史実から、誤りが明らかになった部分もある。しかし、それは史実を踏まえて読めば良いのであって、松本が庶民目線から歴史を見る先駆者としての役割を担っていたことに変わりは無いというのが保阪の考えである。
本書の最後には、二つの対談が掲載されている。保阪と作家の阿刀田高の対談では、松本の活躍した時代は月刊誌・週刊誌の発行も増え、松本ともとに五味康祐、柴田錬三郎、池波正太郎、司馬遼太郎と多くの新しい作家達が続々と世に出てきた時代だったことを語り合っている。また、阿刀田は「自分は黒塗り教科書世代で、ある日突然歴史がひっくり返って、『嘘の歴史を習っていた』という思いが深かったので、本当の事を知りたいという欲望に松本の著作は応えてくれた」という感想は世代史観そのものである。
二つ目の対談は、保阪と加藤陽子の対談だが、天皇機関説に対する松本の姿勢、学問としての歴史の意味、松本と同年代の埴谷雄嵩、太宰治、大岡昇平たちは何故二・二六を語らなかったのかなどを語っている。
私の様な戦後生まれとしては「昭和史発掘」や「日本の黒い霧」の対象の時代は書かれた歴史知識であって、同時代的に体感できた世代ではない。戦中の「転向」とか、戦後の「公職追放」については戦中派の父と雑談したことは有っても、彼の断片的な体験談でしかなかった。そう考えると、もっと父親と話す機会を持って、松本清張の昭和史観に対する戦中派世代としての史観も聞きたかったと、今更ながらに思いを馳せた読書だった。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





