中華料理と日本人【岩間一弘】
中華料理と日本人
| 書籍名 | 中華料理と日本人 |
|---|---|
| 著者名 | 岩間一弘 |
| 出版社 | 中公新書(290p) |
| 発刊日 | 2025.06.25 |
| 希望小売価格 | 1,166円 |
| 書評日 | 2025.10.17 |
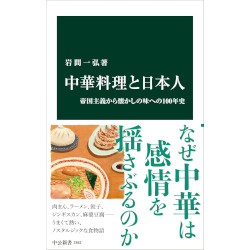
本格中華から町中華、最近のガチ中華にいたるまで、中華料理はこの国の食文化としてすっかり定着している。グルメ番組や料理本でも、中華は定番のひとつになっている。そんなふうにわれわれの生活に欠かせないものとなった料理について、今さら中華料理と日本人とは? と正面きって問いを立てること自体が野暮という気がしないでもない。でも著者の岩間はその野暮をあえて引き受けて本書を著した。サブタイトルは「帝国主義から懐かしの味への100年史」。
食の文化交流史を専門とする著者が、日本の中華料理を考えるに際して取る視点は「ポスト帝国主義」というもの。ポスト帝国主義とは簡単に言えば、「帝国(中国を侵略した大日本帝国)が終わった後でもその影響や遺産に思いをめぐらすこと」だ。
「定番中国料理の品々のルーツをいくつかたどっていけば、日本における中華料理の普及に帝国主義が深く関わっていることがわかってくる。……今の日本で人気のある定番中華料理のいくつかは、アジアに勢力圏を広げた日本帝国の飲食文化として受け入れられ始め、さらに敗戦後にはアジアから撤退した日本人の心身を癒すコンフォート・フード(心地よい食べ物)として広まったのではないか」
こんな観点から著者は、肉まん、ジンギスカン、餃子、ラーメン、ウーロン茶など、われわれになじみ深い中華の品々をひとつひとつ、それが日本人になじみ深い食として定着する過程を調べている。
それを追いかける前に、中華料理が本格的にこの国に入ってきたのはいつなのか。明治初期の中華料理は江戸時代の卓袱(しっぽく)料理の影響が強かったが、中華料理(当時は「支那料理」)が広く日本人に食べられるようになったのは日清戦争後だった。長崎では今のちゃんぽんのスタイルをつくった「四海樓」が開業した。広東出身者が多い横浜のチャイナタウンでは、広東料理の点心シュウマイが名物となった。また日清戦争後の日本留学ブームで東京の神田・神保町に中国人留学生街が形成され、「漢陽楼」(周恩来がひいきにした)や「維新號」(今は銀座にある)が開店した。関東大震災後には屋台の「南京蕎麦屋」が多く生まれ、やがて店を構えることになって、東京は「支那料理屋の全盛時代」を迎える。こうした下地があるなかで日本の中国東北地方への進出が始まり、多くの日本人が中国大陸で現地の料理に接することとなった。
著者がまず取り上げているのは、肉まん。肉まん(「豚饅頭」)の老舗として有名なのは神戸の「老詳記」だが、一部の店でしか買えなかった肉まんを広く普及させたのは昭和初期、東京の中村屋だった。中村屋を創業した相馬愛蔵夫妻がアジア主義に影響を受けインドの独立運動家ボースをかくまったことは有名だ。相馬夫妻は1925年、張作霖が支配する旧満洲地域に旅行し、そこで味わった「包子(パオズ)」を日本人の好みに合わせた味に改良し「支那饅頭」として売り出した。
満洲国が生まれると、満洲を宣伝する国策のなかで、肉まんは餃子やジンギスカンと並んで代表的な「満洲料理」「お国料理」として紹介され、レシピ本が出版されたりしている。それは戦後にも引き継がれた。「満洲国を代表する食べ物であった肉まんは、日本の敗戦と満洲国の崩壊後、満洲を懐かしむ食べ物の一つになった。それは、引き揚げのときの苦難を思い出すだけでなく、ときには食べ物を恵んでくれた中国人に対する感謝や、満洲に入植していたことを悔やむ気持ちを呼び起こす食べ物として小説に描かれた」。
餃子も肉まんと同じく、あるいはそれ以上に満洲国と密接にかかわっている。餃子は明治末ごろから「豚饅頭(鍋貼餃子)」という名で蒸し餃子や焼き餃子が紹介されていた。でも多くの日本人が餃子を食べ始めたのは満洲国ができてから。「満洲料理」として真っ先に挙げられるのが餃子だった。特に日本から満洲に渡った開拓団員や下級軍人にとっては、本格的な中華料理を食べる機会はほとんどなく、一方、日本食より安い餃子や麺類は日々の食べ物だった。開拓団では小麦粉も肉も葱や白菜も自家生産できたから、開拓団に適した料理でもあった。「ギョウザ」という名称も満洲の日本人社会で生まれたものだが、山東省の中国語の発音に基づくもののようだ。
敗戦後、満洲から120万人の引揚者が日本へ帰ってきた。彼らが餃子を広めることで戦後社会で餃子の流行が生まれ、国民食と呼ばれるまでになった。はじめ引揚者は渋谷や神田で店を開いた。渋谷の「有楽」や「珉珉」が有名で、「珉珉」では餡にニンニクをたっぷり入れた焼き餃子が「スタミナ食」として人気になり、これが日本式餃子のスタンダードになった。なお、現在の「珉珉」は渋谷の店で修業した人間が大阪で開店し、チェーン化したもの(ちなみに小生の家の近所には「ぎょうざの満洲」がある)。著者はこう分析する。
「戦後の日本社会は、引揚者に対して差別と軽蔑、哀れみに混じった複雑な感情を抱いており、それが引揚者を傷つけた。……満洲国とそこからの引揚者に対する分裂した見方は、満洲から伝わった餃子に対する記憶や感情に反映された。しかし、それと同時に餃子は、日本帝国の崩壊に関わるさまざまな負の感情を癒し、戦後の日本社会における対立や分裂を解消するコンフォート・フードにもなった」
ラーメンも似たような経過をたどって定着した。ラーメンは明治期に外国人居留地が廃止された後、華僑がはじめた「南京そば」が各地に広がり、「支那そば」として食されるようになった。有名なのは浅草の「来々軒」で、一日数千人の客が来るほど繁盛していたという。
戦後、各地のご当地ラーメンに深く関わったのも引揚者だった。札幌では、天津からの引揚者が始めたのが戦後札幌ラーメン店の第一号とされている。また、満鉄に勤めていた引揚者が味噌ラーメンを発案した。白濁豚骨スープの博多ラーメンは、奉天にいた元兵士が現地で食べた「十銭そば」の味を再現したものだという。ラーメンが国民食になるのに貢献したのは日本人ばかりでない。インスタントラーメンやカップ麺を普及させた日清食品の創業者は日本統治下に生まれた台湾人だった。
ウーロン茶の場合は、いささか事情が異なる。ウーロン茶は中国南部で栽培される茶で、広東、福建、台湾が主な産地とされる。台湾は日清戦争後に日本の植民地となったが、その最大の輸出品がウーロン茶だった。東京の銀座に台湾喫茶店が生まれ、台湾スイーツである愛玉ゼリーの店もできるなど、その後の「支那趣味」に先駆けて「台湾趣味」が生まれた。東京や大阪で開かれた勧業博覧会には台湾館がつくられ、ウーロン茶が提供された(ただ、お茶を提供する台湾少女の髪型や纏足、服装が注目されるなど、植民者が「土人」を見る視線だった)。こんなふうに戦前の日本社会では一部とはいえウーロン茶が飲まれていたが、戦後、その記憶は忘れられた。
ウーロン茶が復活するのは、1970年代に日中国交回復後の「中国商品ブーム」のひとつとしてだった。「痩せる中国茶」としてまず女性に人気になり、1980年代に入ると缶入りウーロン茶が発売された。サントリーはウーロン茶の広告を大々的に仕掛けた。これは小生も記憶しているが、台湾を想起させるものはまったくなく、若い中国人カップルが中国語で「いつでも夢を」をデュエットするなど、「若い中国人のすがすがしいイメージが、多くの日本人視聴者にノスタルジアを感じさせた」。この一連の宣伝は、本書で引用される高山宏が喝破するように、西洋人のオリエンタリズムを借用(無意識に内面化?)した日本人による「エキゾチック・スペースとしての支那のイメージ」だったろう。
こんなふうに見てくると、いま中華料理と呼ばれるものは、横浜や神戸などチャイナタウンの華僑が元になって広めたものと、日本人が中国や台湾から持ってきて広めたものと、大別して二つの流れがあることが分かる。その二つの系譜は今では入り混じって定着している。また著者はジンギスカン料理を、帝国主義と料理の関係を典型的に示す例として取り上げている。ただジンギスカンは今、いわゆる中華料理とは違うジャンルと考えられるので、ここでは紹介しなかった。興味ある方は本書を読んでいただきたい。
文章や構成にいささか生硬なところもあるけれど、いろんな中華料理の来歴、来し方を知って勉強になった。それを知ってるか知らないかで、味わいも変わってくるに違いない。さて、今日は餃子にしようか、ラーメンにしようか。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





