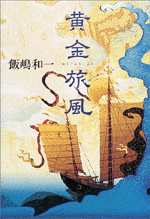|
|
|
飯嶋和一著 小学館(488p)2004.4.1 1900円+税 |
|
私が初めて飯嶋和一を知ったのは『神無き月十番目の夜』(1997)だった。徳川家の300年に渡る支配が確立する前夜、常陸の地侍、百姓がその地の大名・佐竹氏に反乱を起こし、村全体が一人残らず抹殺されてしまうさまを緊迫した文章で描いた力作だった。読後、いつまでも重い塊のようなものが胸に残った。 その後、旧作である『雷電本紀』(1994)、処女作で唯一の現代小説(ボクシング小説)『汝ふたたび故郷へ帰れず』(1988)を読み、新作の『始祖鳥記』(2000)を追っかけるという具合に、飯嶋和一にはまった。ちなみに、これで寡作な飯嶋の全作品。 どんな小説でも、それを読んでいる間は現実を離れ、仮構された小説の時空に入り込んでしまうものだけれど、飯嶋和一の小説は、ほんとうにその時代にタイムトリップしたかのような感覚を覚える磁力を持っている。そしてそこで描かれるのは、いつでも変わらない。時代の壁に精いっぱい抗い、戦って、敗れていく者たち。 この『黄金旅風』で読む者をトリップさせてくれる先は徳川初期の長崎。南蛮貿易が盛んだった時代から、切支丹弾圧へと舵が切られ、鎖国へと向かう寛永年間の港町だ。 主人公は2人。朱印船貿易を営む家に生まれ、放蕩息子と言われながら、暗殺された父を継いで長崎代官となった平左衛門。手の着けられない悪童だったが、火消組の頭となった才助。2人は、今は壊された教会のセミナリオに入れられ、日本人を牛馬のように扱う修道士に反抗した仲間でもあった。 野心むき出しの長崎奉行が隠れ切支丹を暴いては殺し、呂宋(ルソン)侵略を企むなかで、平左衛門と才助は朱印船貿易と長崎の町の自治を守るために奮闘してゆく。 と、筋を追えばそういうことになるが、この小説でなにより見事なのは、平左衛門や才助たちを取りまく圧倒的な自然の力、海や炎や巨木の描写ではないかと思う。 「波が高く、燐光が妖しく海面を彩る夜、うねりながら波は白く燃え続け、集合と離散を絶え間なく繰り返した。その様は、昼に見る単なる水の集まりとはとても映らず、知力と感情を備えた巨大な生命体としか思われなかった。荒波が打ち寄せ砕け散る音しか聞こえず、間断なくうねりながら寄せてきては岩にぶつかり白い飛沫を噴き上げては返していく。海の鼓動と意志とを確かに感じた。その巨大な生命体の前では己の力や意志など何の価値も意味も持たない、取るに足らないものとして消え失せた」 海や炎や巨木は人間を超えるものとして、平左衛門や才助や長崎奉行や将軍家光らがうごめく舞台を取り巻き、彼らをながめている。といって、ここに神の視点からみたある種のニヒリズム、運命論的なあきらめがあるわけではない。逆に、そうした人間を超えるものに取り囲まれながら、作者はあらん限りのエネルギーで語り、行動しつづける登場人物たちに寄り添っている。 この引用からも分かるように、飯嶋和一はうまい小説家ではない。むしろ、確信犯的に下手な小説家だと言ったほうがよいかもしれない。よくある雰囲気描写というやつを、飯嶋はいっさいやらない。会話の妙というやつも無視して、登場人物は長い独白のように飽くことなく語りつづける。そして、作者自身の思いが生硬とも思える言葉で表白される。 でも、そんな「下手さ」をものともせず、物語のダイナミズムが読む者をぐいぐいと引っ張ってゆく。大火のなか、取り残された娘を助けようとして、才助が炎に飲まれてゆくシーンなど、自分自身もそのなかにいるように炎の熱を感じ、息苦しくなってくる。 また小説の結構を無視するように差しはさまれ、そのまま消えてしまったりする人物の断章も忘れがたい。 長崎の隠れ切支丹に要請され、ジャンク船の水主(かこ)を装って密入国してくる、「精神も肉体も鍛え上げた筋金入り」の日本人パードレ。 あるいは鋳物師の職人・真三郎(航海法やジャンク船の構造、鋳物など技術にこだわるのも飯嶋の面白いところ)。真三郎は知らずにつくらされた母子像が「踏み絵」に使われたのにショックを受け、潜伏するパードレを装って死期を迎えた隠れ切支丹の懺悔を聞き、彼らの最後のやすらぎに接することで自分自身を取り戻す。 この本のタイトルである「黄金」とは、呂宋やカンボジアから長崎まで海を渡ってくる黄金蝶のことであり、またベトナムやカンボジアから運ばれる黄金の繭玉のことでもある。逼塞するこの国の過去と現在に、海の向こうから「旅」の果てにやってくる「風」なのだ。その黄金の繭を、子供たちが受け取る場面。 「弥兵衛が子らを促して両手を出させ、小さな手のひらに黄金の繭玉を五つづつ載せ始めた。弥兵衛を取り囲んだ子どもらが、我も我もと手を差し出し始めた。次々と差し出される小さな手に弥兵衛が金色の繭玉を載せていく様を眺めながら、平左衛門は黄金の光を発する繭玉よりも、たくさんの花のような手のひらの輝きに打たれていた」 平左衛門は最後の海洋冒険商人として、海の向こうからやってくる、たおやかな「風」の匂いに満ちた人物として造形されている。作者が鎖国前夜を舞台に選んだことからも想像できるように、平右衛門と才助は歴史の大きな渦に飲み込まれ、敗れてゆく。しかし飯嶋和一の主人公は、ほかのどの作品の主人公とも同じく、現実には敗れてもその魂において「敗れざる者たち」なのだ。(雄) |