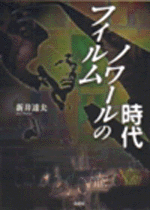|
|
|
「フィルムノワールの時代」 新井達夫著 鳥影社(256p)2002.7.25 2200円 |
|
それなのに、書店でぱらぱらとページをめくっていて「市井の映画ファンとして」という言葉に引かれて、ついついこの本を買ってしまった。後で経歴を見ると「映像作家・CM作家」とあったから、厳密には「市井のファン」とは言えないかもしれないが、プロの物書きではない。こちらも市井の一ファンとして、友情のようなものを感じたのだ。 本のタイトルになっている「フィルムノワール」とは、1940年代から50年代にかけてアメリカでつくられた一連の犯罪映画群のことを指す。モノクロームの画面に光と影が交錯し、男は悪女に魅入られ、主人公はたいてい破滅してゆく。フィルムノワールが好きだと言えば、映画ファンはその言葉を発した人の好みを一瞬にして察知する。 フィルムノワールは、ナチス・ドイツを逃れてハリウッドに移り住んだ監督たちによってつくりだされ、やがてハワード・ホークス、ジョン・ヒューストンといった生粋のアメリカ生まれの巨匠たちが傑作を生みだしていった。 この本はアメリカ生まれの巨匠にはあっさり触れるだけで、ドイツ・中欧系のフリッツ・ラング、ロバート・シオドマク、マイケル・カーティスら、ヨーロッパの美意識と退廃を引き受けてノワールをつくりあげていった監督たちに光を当てていく。そこに著者の主張が感じられる。 なにより作品を追いかける著者の執念がすごい。映画館で見た記憶をたどり、ビデオをさがし、外国まで出かけて日本未公開の映画を見るし、未輸入ビデオを入手する。「私は現物を見ないで映画を語ることに抵抗を感ずる者だ」とさりげなく記しているが、そうする者がいる状況に対する著者の自負とも言えるだろう。 「私はフィルムノワールの欠くべからざる条件のひとつとして、悪夢のような世界があると考えている」「フィルムノワールという形をとって現れた映画は、幸せになれない人間を描く映画だとも言える」「フィルムノワールにとって風俗描写は、話の本筋と同じほど重要である」 このあたりには、長年、フィルムノワールを見つづけた著者の思いが込められていよう。僕も、著者の指摘に深くうなづく。難解な映画評論が幅をきかすなか(フィルムノワールの記号論的分析とか)、オーソドックスな視点と素直な文章も素敵だ。 それにしても、と思う。著者と僕とは6歳違いだが、著者の濃密なノワール体験と、僕の「遅れてきた」ノワール体験の差はなんなのだろう。著者は1955年、中学2年のとき新宿地球座で『マルタの鷹』を見たという。50年代半ばといえばフィルムノワールが終わろうとしている時代だが、ここから著者はノワールにのめりこんでいったらしい。 僕が映画を見始めたのもそのころだけれど東映専門で、中学に入って洋画を見るようになった60年代には、もうフィルムノワールはどこにもなかった。眼をこらせば新宿や浅草の三番館にはかかっていたのだろうし、それらしき看板を見た覚えもあるが、年相応のファンとして『ベン・ハー』や『アラモ』やアイドル映画(ヘイリー・ミルズが好きでした)に入れあげて、大人の匂いのするフィルムノワールには近づかなかった。 思い出してみると、僕が初めてノワール、あるいはノワールの影を持つ映画に接したのは、西部劇リバイバル・ブームのなかで見た『シェーン』(著者によれば、これは西部劇ではなくフィルムノワールだ)か『大砂塵』、あるいは名画座で見た『第三の男』だろうか。 高校・大学時代に見たゴダールの『メイド・インUSA』や『アルファビル』『気狂いピエロ』は、フィルムノワールをゴダール流に解体・再構築したオマージュでありパロディーでもあるが、ノワールを見ずに彼の映画をいっぱし語ったりしていたのだから、いまから思うと恥ずかしい。 僕が本格的にフィルムノワールを見るようになったのは、著者に遅れること十数年、会社勤めをはじめた70年代に入ってからのことになる(60年代日本映画の中平康や深作欣二にノワールの影の影が見えるのは別として)。 この時期、70年代フィルムノワールともいうべき『ダーティーハリー』『ロンググッドバイ』『チャイナタウン』『800万の死にざま』『タクシードライバー』などが、ヨーロッパからは『仁義』『リスボン特急』『フリック・ストーリー』『ローマに散る』などが相次いで公開されて、僕はこれらの映画にのめり込んでいった。 ついでに言うと、ロバート・ミッチャムがマーロウを演じた『さらば愛しき人よ』をこの時代の名作と評する若い論者に出会ったが、僕の記憶では、同時代のひりひりした感性に乏しいノスタルジックなだけの映画だった。 もっともこれらの作品は、フィルムノワールというよりハードボイルドと言ったほうが正確かもしれない。両者はかなりの部分で重なり合ってはいるが、同じではない。僕の場合、ハードボイルドへの興味がより大きかったが、そして著者ほど徹底してはいないが、そこから50年代の作品へとさかのぼっていくことになった。 著者は「あとがき」で、「一人立ち寄った酒場で、偶然隣り合わせた自分とよく似た年格好の初老の男と口を利くことがある。話が弾み、ふと気づいてみると映画の話に熱中していたりする」と書いている。僕もいつかどこかで著者とカウンターで隣り合わせることがあれば、この本に敬意を表し、70年代フィルムノワールについて語り合うのを楽しみにしていよう。(雄) |